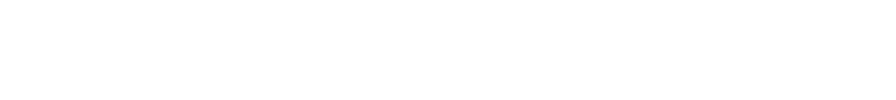非破壊検査の「なぜ」「どうやって」がわかる!主要な検査手法(RT, UT, MT, PT, ET)の原理と検出能力を徹底解説
の原理と検出能力を徹底解説.jpg)
非破壊検査には、超音波、放射線、磁気、渦電流など、さまざまな物理現象を利用した検査技術があり、検査対象や目的に応じて使い分けられています。適切な検査結果を得るためには、各手法が「何を」「どのように」検出できるのかを知ることが不可欠です。
この記事では、「各検査手法(RT, UT, MT, PT, ETなど)の仕組みや検出能力を、さらに深掘りして知りたい」という専門的な関心を持つ皆さまに向けて、主要な非破壊検査手法の基本的な仕組み、検出能力、そして適用上の特徴を、詳しく解説していきます。
非破壊検査とは:安全と信頼性を支える技術の基本

非破壊検査とは、物を壊さずにその内部や表面のきず、あるいは劣化の状況を調べ出す検査技術のことです。対象物にダメージを与えたり、分解したりすることなく、継続して安全に使用できるか(健全性)を検査します。
この技術は、製品や構造物の信頼性を向上させ、寿命を長くすることに役立ちます。また、使用中の設備に適用することで、長期的な有効活用を可能にし、廃棄物を少なくして自然環境を維持するためにも非常に有効です。
検査対象は、原子力発電所、プラント、鉄道、航空機、橋梁、ビル、地中埋設物など、社会資本すべてにわたります。検査の時期は、完成前の検査から、使用中の定期検査、保守検査など、交換廃棄までのすべての工程で実施され、「安全と安心」を提供しています。
非破壊検査技術の基礎用語と定義
非破壊検査の分野では、JIS(日本産業規格)によって細かく用語が定められており、略記号としてNDT、NDI、NDEが用いられます。
非破壊試験(NDT:Non Destructive Testing)
素材や製品を破壊せずに、きずの有無、その存在位置、大きさ、形状、分布状態などを調べる「試験」行為そのものを指します。
非破壊検査(NDI:Non Destructive Inspection)
非破壊試験の結果から、規格などによる基準に従って合否を判定する方法を指します。
非破壊評価(NDE:Non Destructive Evaluation)
非破壊試験で得られた指示を、試験体の性質または使用性能の面から総合的に解析・評価することを指します。
また、「きず」と「欠陥」についても厳密に区別されます。
きず
非破壊検査で見つけ出された意図しない不連続部(discontinuity)を仮名表記で「きず」と呼びます。その存在自体が直ちに有害であるとはいえないため、よりソフトな表現が用いられます。
欠陥
検査の結果として有害とされる「きず」が「欠陥」と呼ばれます。
表面および表面近傍のきずを検出する検査手法
ここでは、物の表面やそのすぐ下に隠れたきずを見つけ出す検査手法を解説します。
目視試験(VT:Visual Testing)
目視試験は、人間の目で見て観察する試験方法です。試験体の表面のきずの有無、凹凸、変形などを肉眼で直接観察(直視)する方法や、拡大鏡、鏡、ボアスコープやCCDカメラなどの光学機器を用いて間接的に観察する方法があります。
特別な検査装置が不要であり、手早く簡単に調べられます。ツールや治具を用いることで、角変形、目違い、アンダーカット、余盛角度など、目視検査でしか検出できない異常を見つけられます。熟練者が行う場合、比較的小さなきずまで速やかに検出可能です。
日本ではVTの技術者資格は存在しませんが、非破壊試験技術者には、特定の最小文字を30cm以上離れて読めることなど、近距離視力が必須条件とされています。
浸透探傷試験(PT:Penetrant Testing)
表面に開口している微細な割れやきずを、色や光で可視化する手法です。特殊な溶剤(浸透液、着色または蛍光性)を試験体の表面に開口しているきずに浸透させます。その後、余分な浸透液を除去し、現像剤を塗布すると、きず内部に浸透していた液体が毛細管現象によって表面に吸い出され、肉眼で識別できる指示模様(きず模様)として現れます。
多孔質以外のあらゆる材料(金属、非金属)表面開口きずの検出に適しており、1回の操作で、あらゆる方向のきずを検出することが可能です。装置が不要で携帯性が良く、電源も不要な場合が多いというメリットがあります。
ただし、内部きずの検査は適用不可です。木材や陶器など微細な空孔が多い多孔質材料や、表面粗さが荒い場合は適用が困難です。
磁粉探傷試験(MT:Magnetic particle Testing)
強磁性体の表面やごく浅い内部きずの検出に優れた手法です。強磁性体(鉄、ニッケル、コバルトなど)を磁化させ、表面や表面直下にきずがあると、磁束がさえぎられ空間へ漏洩磁束が発生します。そこに磁性体の微粉末(磁粉)を散布すると、磁粉がきず部に吸着し、きず模様として可視化されます。
強磁性材料のみに適用できます。表面きずの検出能力に優れているほか、表面直下(約2〜3mm程度)のきずも検出可能です。複雑な形状の部品でも検出可能で、蛍光磁粉を使用すると微細なきずの検出に優れます。
なお、非磁性材(アルミ合金、ステンレス鋼など)には適用できません。
渦電流探傷試験(ET:Eddy current Testing)
非接触で高速検査が可能であり、導電性材料に適用される手法です。探傷コイルに高周波電流を流し、電磁誘導により検査対象物(導体)の表面に渦電流を発生させます。きずや導電率の変化があると渦電流の流れが変わり、この変化を電磁誘導の変化として検出し、きずの有無や材質の変化を判定します。
磁性・非磁性に関わらず、導電性のある対象物に適用できます。被検査物との間に媒体を必要とせず非接触で行えるため、検査速度が速く、高速での探傷が可能です。試験結果が電気信号で得られるため、自動化に適しています。導電率の違いを利用して、金属材料の材質判別や合金判別にも応用可能です。
ただし、導電性のない材料や、深部の内部きずの検査は適用できません。
内部構造や体積きずを検出する検査手法
目に見えない材料の内部、溶接部、構造物の内部に存在するきずや空洞を検出する手法です。
放射線透過試験(RT:Radiographic Testing)
病院のレントゲン撮影と同じ原理で、内部きずの検出方法として非常に信頼性が高く、広く使われています。試験体にX線やγ線(ガンマ線)といった放射線を照射します。透過した放射線はX線フィルムやイメージングプレート(IP)に投影され、きず(空洞など)がある部分と、健全な部分とでは放射線の透過量に差が生じ、フィルム上に濃度差としてきずの像が形成されます。
溶接の溶け込み不足やブローホールのような、体積を持つ内部きず(球状きず)の検出を目的としており、詳細な確認が可能です。放射線が通過する物なら、金属・非金属材料によらず適用できます。判定結果が写真やデータとして残るため、記録性に優れています。配管などの内部の状態確認にも適用できます。
放射線を取り扱うため、安全管理が必要であり、防爆設備が必要となる場合があります。また、放射線の進行方向に垂直な平面状の割れは検出されにくいため、表面きず検出目的の検査と併用することが推奨されます。近年では、X線CT (コンピュータ断層撮影) や、高感度なIPを用いたデジタルラジオグラフィが普及しています。
超音波探傷試験(UT:Ultrasonic Testing)
きずの位置や大きさを正確に測定できる、非破壊検査の代表的な方法の一つです。探触子(プローブ)を使って、人間の耳には聞こえない高い周波数(実用的には1〜10MHz)の超音波(弾性波)反射波の到達時間や強度を測定・解析することで、きずの有無、位置、大きさを検出します。
材料内部の面形状を持つ割れ(平面状きず)に対して検出精度が高いです。溶接部や鍛造品の内部きずの検出に広く適用されます。機器を分解せずに、外側からの検査が可能であり、きずの位置を正確に知ることができます。結果がリアルタイムで得られます。
鋳造品などの粗粒材は超音波が乱反射しやすく、正確な検査が困難な場合があります。しかし近年、フェーズドアレイ探傷法などの開発により、きずの寸法や形状の推定が可能となってきました。
特殊な現象や応用技術を利用する検査手法
上記主要6手法(VT, PT, MT, ET, RT, UT)の他にも、特定の目的や状況に対応するため、多様な技術が使われています。
ひずみ測定(SM / ST:Stress Measurement / Strain gauge Testing)
構造物に生じるひずみや応力の状態を調べる手法です。電気抵抗ひずみゲージを構造物に貼付し、荷重によって生じるひずみ値を測定します。このひずみ値と材料の弾性係数を用いて応力を求めます。
プラントの貯蔵タンク、橋、船舶、航空機などの応力変化を捉えるために利用され、設計上の指針を与えることができます。ひずみゲージ式変換器を使うことで、荷重、圧力、加速度、変位など、さまざまな物理量を正確に測定できます。
アコースティック・エミッション(AE:Acoustic Emission)
材料の変形や破壊の初期徴候を音として捉える手法です。材料が変形または破壊(割れが発生・進行)した際に、内部に蓄積されたエネルギーが解放され、弾性波(音波)として放出されます。この弾性波を高感度センサーで測定します。
割れ発生の初期徴候を検出可能であり、運転中や負荷をかけている状態での割れ発生や進行状態をリアルタイムで監視するのに使用されます。
傷の判定には非常に高いスキルが必要とされます。
サーモグラフィ試験(IRT:Infrared Ray Testing)
熱を利用して、表面下の異常を検出する非接触型の検査手法です。赤外線カメラ(サーモグラフィ)を用いて、機器や建築物の表面温度分布の画像を得ます。きずや剥離部、空洞がある場合、健全な部分と比べて熱の伝わり方や放熱に差が生じるため、表面温度に違いが現れ、異常部を検出します。
非破壊・非接触型であり、対象物に触れずに異常の有無を手軽かつ正確に検査できます。特に、建築物の外壁剥離調査など、打診法のリスク回避が必要なインフラ点検に効果的です。
非破壊検査の進化
ここで紹介した技術や検査手法以外にも、非破壊検査の分野での研究開発は続けられており、今後も人々の生活を豊かにするために非破壊検査は進化していくことが予想されます。