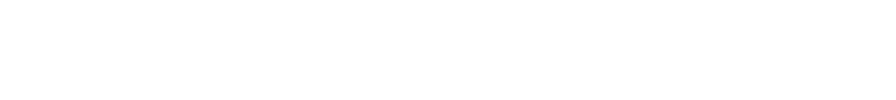非破壊検査とは?〜社会の安全を支える、壊さない検査技術のすべて〜

私たちが普段、安心して暮らしたり、乗り物に乗ったりできるのは、目に見えないところで「安全」が確認されているからです。その安全を支える大切な技術のひとつが「非破壊検査(ひはかいけんさ)」です。
この記事では、非破壊検査が一体どんな技術で、なぜ私たちにとって重要なのかを、分かりやすく総合的に解説します。
もし、この記事を読んで「もっと詳しく知りたい」「うちの製品にも活用できる?」と感じた方のために今後、さらに詳しい情報を解説する補足記事を公開いたします。
非破壊検査とは?定義と私たちとの関わり

非破壊検査とは、その名の通り、「物を壊さずに」その内部のきずや表面の傷、あるいは劣化の状況を調べ出す検査技術のことです。対象物にダメージを与えたり分解したりすることなく、健全性(問題なく継続して安全に使用できるか)を評価する方法です。
非破壊検査は英語で「Non Destructive Inspection」と呼ばれ、略してNDI、あるいは「Non Destructive Testing」(非破壊試験)を略してNDTとも呼ばれます。
この非破壊検査の技術は、素材からの加工工程や完成時の製品の検査、設備の建設時の検査などに適用されることで、製品や設備の信頼性を高め、寿命を長くすることに役立っています。
身近な「非破壊検査」の具体例
非破壊検査と聞くと難しく感じるかもしれません。しかし、実は私たちは日常生活の中で、無意識に非破壊検査を行っていたり、その恩恵を受けていたりします。具体例をご紹介しましょう。
スイカを叩く
軽く叩いて反響音の違いから成熟度を確かめる行為は、非破壊検査の一種です。対象物を叩いて音の反響を確認する打音検査も、広く採用されている検査方法のひとつです。ご自宅に届いた封筒をライトなどの光で透かして中身を確認する行為も一種の非破壊検査です。
病院での検査
医療分野で使われるX線撮影(レントゲン)や超音波(エコー)検査も、同じ原理を用いた非破壊検査です。検査のたびに腹部の切開をしたり、皮膚や骨を傷つけることはできませんので、身体に傷をつけることなく検査が行われます。
空港での手荷物検査
航空機に搭乗する際に行われるX線による手荷物検査も、物を壊さずに内部を確認する非破壊検査の一種です。旅行に出かけるごとに手荷物に持つが破壊されていては折角の旅行気分も台無しですよね。
また、歴史的な事例として、大阪城の柱の継ぎ方が、非破壊検査の放射線の検査で60年ぶりに解明されたというエピソードもあります。大切な手まりの音色の秘密を放射線で壊さずに調べたり、薬師寺東塔の心柱内部の空洞の状態が確認されたりした事例もあります。
非破壊検査の目的と社会的な重要性
非破壊検査は、単に「傷を探す」だけでなく、社会の安全や持続可能性に対して非常に重要な役割を果たしています。
最大の目的は「信頼性の確保」と「安全の提供」
非破壊検査の主な目的は以下の3つです。
1. 信頼性を確保する
一定期間内に所期の性能を満たすことができる確率である「信頼度」を確保することが最大の目的です。
2. コスト低減
製造工程の初期や中間検査として適用することで、不良品を早期に発見・排除し、工数削減や経費の節約となり、生産コスト低減を図ることができます。また、不意の故障や事故による経済的損失を回避する目的もあります。
3. 製造技術の改良を促す
不具合を正確に知り、製造工程へフィードバックすることで、製品の製造技術の改良を図ります。
さらに、使用中の設備などに対し保守検査の一環として非破壊試験を適用することにより、長期にわたって有効に活用することを可能にします。これにより、廃棄物を少なくして自然環境を維持するために非常に有効な技術となっています。
インフラ老朽化と労働力不足への対応
特に非破壊検査の活用が強く期待されている分野が、生活や産業の基盤となるインフラの安全確認です。
日本では、高度経済成長期に造られた道路橋やトンネルなどのインフラが老朽化し、安全性の確保が喫緊の課題となっています。これらのインフラは継続的に使用されているため、壊したり分解しての調査は困難です。また同時に、少子高齢化に伴う労働人口の減少により、安全確認を行うための人手も足りていません。
非破壊検査は、対象物を壊さずに内部の状態やダメージの進行を確認できるため、インフラの点検に活用しようという動きが広がっています。
非破壊検査の主要な種類と特徴
非破壊検査には、超音波、放射線、磁気、渦電流など、さまざまな物理現象を利用した検査技術があり、検査対象や目的に応じて使い分け、あるいは組み合わせて使用されます。
代表的な検査方法一覧
ここでは、代表的な非破壊検査の方法と、それぞれの原理、特徴をご紹介します。
| 検査名(略称) | 原理 | 特徴・適用対象 | 課題・適用制限 |
|---|---|---|---|
| 目視検査(VT) | 肉眼や光学機器で表面の状態やきずを観察 | 最もシンプルで基本、特別な装置が不要。 | 熟練度が必要、近距離視力が必須条件とされる。 |
| 浸透探傷試験(PT) | 浸透液を表面開口きずに浸透させ、毛細管現象で可視化 | 多孔質以外のあらゆる材料(金属・非金属)に適用可能。 | 内部検査は不可、多孔質材料や表面粗さが荒い場合は不向き。 |
| 磁粉探傷試験(MT) | 強磁性体を磁化し、漏洩磁束に磁粉を付着させきずを可視化 | 強磁性材料に適用、表面および表面直下のきずを検出。複雑な形状にも適用可能。 | 非磁性材には適用できない。 |
| 渦電流探傷試験(ET) | 導体に発生した渦電流の変化からきずを検出 | 導電性のある対象物に非接触かつ高速で探傷可能、自動化に適する。 | 導電性のない材料や内部きずの検査は適用不可。 |
| 放射線透過試験(RT) | 放射線(X線/γ線)を透過させ、フィルム等に投影し内部きずを検出 | 放射線が通過する物なら材料によらず適用可、内部(体積きず)の詳細確認、記録性に優れる。 | 放射線安全管理が必要、防爆設備が必要。 |
| 超音波探傷試験(UT) | 超音波を伝搬させ、きずからの反射波を利用して位置と大きさを測定 | 溶接部や鍛造品の内部きず(平面状のきず)に検出精度が高い。外側からの検査が可能。 | 欠陥形状の判定がやや困難、複雑形状や粗粒材には向かない。 |
| ひずみ測定(ST/SM) | ひずみゲージ等を用いて荷重によるひずみや応力の状態を測定 | 構造物の応力状態を監視し、多様な物理量を測定できる。 | 測定方法が多岐にわたる。 |
| アコースティック・エミッション(AE) | 材料が変形/破壊した際に発生する弾性波を測定 | 割れ発生の初期徴候検出、リアルタイム計測、運転中の監視に使用可。 | 傷の判定に高いスキルが必要。 |
| サーモグラフィ試験(IRT) | 赤外線カメラで表面温度分布の画像を得る | 非破壊・非接触、打診法のリスク回避、外壁剥離調査など。 | – |
その他、漏れ試験 や、近赤外光の透過性を利用し物質濃度を計測する近赤外分光法、電磁波レーダや電磁誘導を用いた地中埋設物の調査 なども非破壊検査に含まれます。
非破壊検査のメリットと課題(デメリット)
非破壊検査は多くのメリットを提供しますが、その活用には考慮すべき課題も存在します。
非破壊検査の主なメリット
非破壊検査のメリットは、主に以下の3点です。
安全性の向上
定期的な非破壊検査により、新たに発生したきずを評価し、設備の停止や事故発生リスクを低減できます。
コストの低減
製造工程の早い段階で不良品を発見し排除することで、全体的な工数の削減、経費の節約となり、生産コスト低減を図ることができます。また、不意の故障による経済的損失の回避にもつながります。
製造技術の改良
試作品に非破壊検査を行い、品質を確認することで、安定した品質が得られるように適用工程の条件を改良しながら確立することができます。
非破壊検査の課題(デメリット)
非破壊検査のデメリットも把握し、活用することが重要です。
検査従事者の育成に時間がかかる
人命に関わる検査手段であるため、規格では検査手法ごとに作業実績やトレーニング時間、試験の要求が厳格に定められており、高い技量レベルに到達するまでに時間を要します。傷の判定に高いスキルが必要な手法もあります(例:AE法)。
初期投資が高額になることがある
浸透探傷検査や磁粉探傷検査は比較的低コストで導入可能ですが、放射線透過検査や超音波探傷検査の装置は高額になることがあります。高度な機能や精度を求めると、装置のコストも高くなります。
検査時間がかかることがある
検査方法や対象物の大きさ、形状、求められる精度によっては、機器のセッティングや多角的な検査が必要となり、時間がかかる場合があります。
非破壊検査の信頼性を担保する資格制度
非破壊検査は専門性が非常に高いため、検査従事者には厳格な技能と知識が求められます。
JISに基づく技術者資格
日本では、ISO9712を元にしたJIS Z 2305「非破壊試験-技術者の資格および認証」によって、技術者の資格認定が定められています。
資格は、放射線透過試験(RT)、超音波探傷試験(UT)、磁粉探傷試験(MT)、浸透探傷試験(PT)、渦電流探傷試験(ET)、ひずみ測定(SM)の計6分野ごとに、レベル1からレベル3まで認定されます。レベル1は易しい順、レベル3は最も高度な資格です。
また、このJIS資格とは別に、日本非破壊検査協会では、レベル3よりもさらに上位の資格として「非破壊検査総合管理技術者」の資格試験を実施しています。
特殊な分野における資格
航空宇宙産業においては、NAS-410を元とした資格が必要とされます。航空機は特に厳しい検査要求があり、機体メーカーやエンジンメーカーが作成した検査マニュアルを遵守し、適切に非破壊検査を運用することで航空安全が守られています。